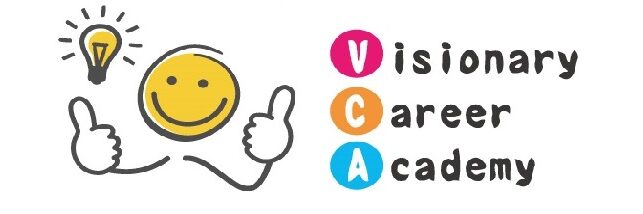不登校の子と親が共に育つ――存在を支える「一緒に育つまなざし」

不登校の子と共に揺れる親の心
不登校の子どもを支える道のりには、たくさんの揺れがあります。
子どもが少し動き出したかと思えば立ち止まり、安心した翌日にはまた不安に揺れる。
同じように、親の心も揺れます。
「大丈夫」と思えた日があっても、翌日には「やっぱり心配」と不安に押しつぶされることもある。
この揺れは、誰かが未熟だから起こるのではなく、親子が一緒に歩んでいるからこそ生まれる自然な揺れなのです。
不登校の子を「育てる」だけではなく、親も育てられる
「子どもを育てる」という言葉は、親が一方的に働きかけるように聞こえます。
けれど実際には、親もまた子どもと関わる中で育てられていく存在です。
子どもの沈黙に耐える力、期待と落胆を繰り返す心のしなやかさ、比べずに見守るまなざし…。
これらはすべて、親自身が不登校の子どもと過ごすなかで培ってきた成長の証です。
存在を支えるエネルギーは「愛」
これまでの6つのまなざしを通して見てきたのは、子どもの「存在(being)」です。
存在は比べられず、形にもしにくいけれど、確かにそこにあるもの。
そして、その存在を支えるエネルギーの源は「愛」です。
ただし、「愛している」と言葉だけで伝えても十分には響きません。
本当に伝わるのは、態度や表情、日常の行動の積み重ねです。
安心してそばにいること、笑顔を向けること、触れ合いのぬくもり――それが存在を支えるエネルギーになります。
親もまた「愛される存在」であること
親自身が「愛されている」という実感を持たないまま、子どもに愛を注ぎ続けることは困難です。
先月終わった朝ドラ「あんぱん」には、こんな場面がありました。
孤児を抱きしめてきた八木が、「子どもたちに必要なのは食べ物や住まい、音楽や物語、そしてもう一つ、人の体温だ」と語るシーンです。
子どもたちは無条件のぬくもりを知らない、と言いながら、八木自身も「自分を抱きしめてくれる人」を求めていることに気づきます。
同じように、親もまた愛される存在です。
だからこそ、支え合える仲間や安心して話せる場を持つことが大切なのです。
一緒に育つまなざし
不登校の子どもを支える中で、親もまた揺れ、学び、育っていきます。
親子は上下の関係ではなく、共に育ち合う存在です。
「揺れても大丈夫」――その言葉を心に置きながら、これからも親子で一緒に歩み続けていけますように。
「教育とは、親と子が共に成長していく営みである。」
― ヨハン・ハインリッヒ・ペスタロッチ (How Gertrude Teaches Her Children, 1801)
文・大久保智弘
公認心理師・スクールカウンセラー/2児の父。
不登校や思春期の親子支援を専門に活動中。
✨ ご案内 ✨
このコラムは、不登校や引きこもりのお子さんをもつ親御さんのためにお届けしています。
「揺れても大丈夫」という視点を日常に取り入れたい方は、ぜひメールマガジンやカウンセリングもご活用ください。