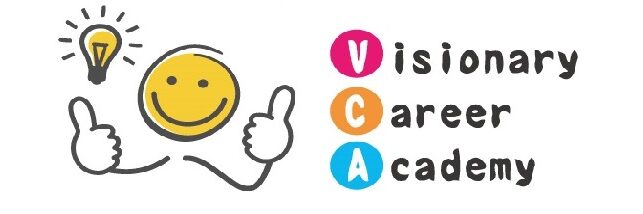沈黙もまた、親子の大切な対話のかたち
──子どもが話さない時間にできること
子どもが学校から帰ってきて、「おかえり」と声をかける。
でも返ってくるのは、目も合わせずにボソッと「あー…」。
表情が暗くて気になり、「何かあったの?」と聞いても、「別に」。
それでもやっぱり心配になって、「なんか、表情が険しいけど…」と重ねて聞くと、
「うるさいな!」と強い口調で返されてしまう──。
こんなとき、親の胸の中には不安が広がります。
「私、嫌われたのかな」「何か地雷を踏んじゃったのかな」と戸惑ってしまう方も多いでしょう。
でも実は、子ども自身も、自分の中にあるモヤモヤをまだうまく言葉にできていないことがあります。
学校でのちょっとしたストレス、人間関係の複雑さ、なんとなくうまくいかなかった一日。
それらを一から説明するのも面倒で、気づけば感情だけが先に溢れてしまう──
その矛先が、いちばん近くて安心できる親に向いてしまうのです。
決して、親が嫌いになったわけではありません。
むしろ、“話せない気持ちごと受けとめてくれる存在”だと信じているからこそ、
不機嫌や反発という形で感情が出てくるのかもしれません。
今回は、そんな沈黙や反発の奥にある子どもの気持ちに、親としてどう寄り添えばいいのかを、一緒に考えてみたいと思います。

子どもとの沈黙が不安に感じるとき
言葉が返ってこない、目も合わせてくれない、なんとなく不機嫌。
そんな子どもの態度に、親は「今、私どう接するのが正解なんだろう?」と迷ってしまうことがあります。
特に、学校で何を感じてきたかなんて、親には見えません。
でも、子どもにとっては「いちいち全部説明するのも面倒」「細かいことを話す気力もない」
そんな気持ちで口数が減っていることもあります。
親に悪気があるわけでも、子どもに敵意があるわけでもないのに、
「話す気になれない空気」と「心配して深く聞く空気」がぶつかってしまうこともあるのです。
沈黙の中にも、関係はちゃんと育っている
思春期や心が揺れているとき、子どもは「話したいけど、うまく言えない」
「伝えたいけど、まとまらない」――そんなもどかしさを抱えていることがあります。
親が無理に引き出そうとすると、かえって子どもは心を閉ざしてしまうことも。
でも、沈黙は関係が壊れている証拠ではありません。
むしろ、「今は話せないけど、ここにいてくれることが安心」という、信頼の表れでもあるのです。
話すことより、「話せる空気」をつくる
親子のコミュニケーションは、言葉のキャッチボールだけではありません。
大切なのは、**「何を言うか」より「どんな空気でそこにいるか」**です。
話しかけても反応がなくても、そばで静かに一緒にいる。
ごはんを並べて「おかえり」とだけ言う。
そんなふうに、**沈黙に寄り添う“まなざし”**が、子どもにとって何よりも安心になることがあります。
沈黙を信じられる親でいるために
子どもの沈黙に耐えるには、親にも心の余裕が必要です。
「今は話せないときなんだ」「言葉にならない気持ちがあるんだ」と思える安心感。
それは、親自身が自分の不安にも優しくできているときに生まれます。
「話してくれない=うまくいっていない」と決めつけず、
「きっと話してくれる時が来る」と信じて、日常を丁寧に過ごしていく。
その姿勢こそが、子どもとの信頼をゆっくりと育んでいきます。
― トマス・ゴードン(臨床心理学者、『親業』より)
文・大久保智弘
公認心理師・スクールカウンセラー/2児の父。
不登校や思春期の親子支援を専門に活動中。
✨ ひとりで抱え込まず、状況を整理してみませんか ✨
このコラムを読みながら、
「これ、うちのことかもしれない」「少し話して整理したい」と感じた方へ。
初回は、今の状況を整理するための
アセスメント(30分・3,000円)からお受けしています。
無理に継続的なカウンセリングをおすすめすることはありませんので、
どうぞ、安心してお問い合わせください。